ショートコラムねだ
中学生のとき「起承転結」っちゅうのを教わった。漢詩には「絶句(ぜっく)」というのがあって、
漢字五つ×4行は五言絶句(ごごんぜっく)、漢字七つ×4行は七言絶句(しちごんぜっく)とい
うとか。次の絶句が例である。高校でも同じ事を教わった。2回も習えば多少は覚えている。
漢字五つ×4行は五言絶句(ごごんぜっく)、漢字七つ×4行は七言絶句(しちごんぜっく)とい
うとか。次の絶句が例である。高校でも同じ事を教わった。2回も習えば多少は覚えている。
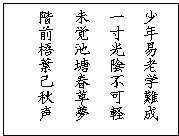
(起)少年老いやすく、学なりがたし
(承)いっすんのこういん軽んずべからず
(転)いまだ覚めずちとうしゅんそうの夢
(結)かいぜんのごよう、既にしゅうせい
人は年をとるのが速く、学問を修めるのは難しい。だからちょっとの時間でも軽視してはいけ
ない。庭の池のつつみの草がまだやっと春が来たと感じているうちに、門前のあおぎりの葉に
はもう秋の気配がしている。
ない。庭の池のつつみの草がまだやっと春が来たと感じているうちに、門前のあおぎりの葉に
はもう秋の気配がしている。
勉強せいよ!というわけであるが、素直な人は表の勉強をし、へそが横についている人は裏
の勉強をする。
の勉強をする。
詩には「詩想」というものがある。その詩想を先ず起こし、その流れを汲んで次の段落を創る。
その次はぐっと変化に富ませ、最後は全体のまとめとして最初の詩想に戻るというのである。
その次はぐっと変化に富ませ、最後は全体のまとめとして最初の詩想に戻るというのである。
文章を書くときにもこのような構造にすると、説得力のあるものになるそうである。
同じ中学校の音楽の先生・・ご婦人であった・・は、"曲には「曲想」というものがあって、よく歌
われる曲の多くは曲想が起承転結にできているのよ。"といっていた。例として、「澄みゆくみ空
に夕日は落ちて」(讃美歌140番「我らの罪とが」)の曲を取り上げていた。おたまじゃくしは描
きにくいゆえ、ドレミでお許しあれ。
われる曲の多くは曲想が起承転結にできているのよ。"といっていた。例として、「澄みゆくみ空
に夕日は落ちて」(讃美歌140番「我らの罪とが」)の曲を取り上げていた。おたまじゃくしは描
きにくいゆえ、ドレミでお許しあれ。
(起)ソ−ソラソミドド−ラ、ソ−ドミドソミレ・・A
(承)ソ−ソラソミドド−ラ、ソ−ドミレドシド・・A´
(転)レ−ドレミファレミ−ソ、ラ−ラソミファミレ・・B
(結)ソ−ソラソミドド−ラ、ソ−ドミレドシド・・A´
先生の説明は"最初の曲想をAとすると、以下Aを少し変えたA´が続き、次は気分をかえたB
がきて、最後はA´にもどってまとめられている。"というものであった。
がきて、最後はA´にもどってまとめられている。"というものであった。
アメイジング・グレイスもほぼ同じ構造でつくられている。確かに曲想は大切である。時にはア
ドリブもいいけれど、曲想をはずれると、ケーキを食べている時にさしみが出てくるようなものに
なる。
ドリブもいいけれど、曲想をはずれると、ケーキを食べている時にさしみが出てくるようなものに
なる。
さて、讃美の詩を書き曲をつくる若さを有する諸君、・・実年齢を問わず・・たまには型にはま
った詩、型にはまった曲もつくってみようぜ。
った詩、型にはまった曲もつくってみようぜ。
その讃美歌が永くみんなに歌われるために。
|
|

